|
|
| HOME > 環境施設整備関連 > ニュースレター
> No.9 2005年 2月号 |
|
No.9 2005年 2月号
|
 |
| |
|
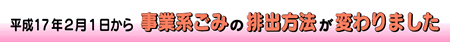
| ごみの分別推進と不正搬入を防止するため 透明・半透明袋への事業所名の記入をお願いいたします。 |
|
| ※事業所名はマジック等で記入して下さい。 |
| ※定期的な搬入ごみ検査を実施いたします。 |
| 事業所名が記入されていないものや、分別がされていないものについては、内容物を確認のうえ事業所へお伺いする事があります。 |
|
| 塩谷広域環境衛生センターでは、事業系ごみの分別推進を図るため、平成11年度より透明または半透明の袋での排出をお願いしておりますが、事業系ごみの搬入検査を行ったところ、可燃ごみの中にペットボトルや古紙類などの資源物が多数見受けられました。また、ごみ処理施設への不正搬入が県内の市町村でも発生しており、塩谷広域圏内においても対策をとる必要があります。 |
| 〜塩谷広域行政組合・矢板市・塩谷町・氏家町・高根沢町・喜連川町〜 |
| 「ニュースレター」及び「ごみ処理行政」に対するご意見・ご提案をお気軽にお寄せください。 |
| 問い合わせ先 |
|
| 〒329-1572 |
栃木県矢板市安沢3622番地1
塩谷広域行政組合
次期ごみ処理施設整備担当 阿久津・鈴木・印南
TEL.0287-48-2760
FAX.0287-48-0463 |
|
|
|
| |
|

